マスター必須!グランビルの法則
株式トレードの大原則はグランビルの法則
株価が移動平均線を抜けた瞬間がなぜ買いポイントなのか?
前回の「具体的な買いポイントはこの瞬間」でお話ししたように、移動平均線の下に株価があると移動平均線がレジスタンスラインとして機能します。
「供給>需要」の状態です。
しかし株価が抜けるということは、その供給を上回るだけの需要があったという事実を表し、その株は勢いがあり強いと判断できます。
さて、その事象を株価と移動平均線の関係において法則化した理論に「グランビルの法則」という法則があります。
インターネットで検索すると驚くほど多くのヒット件数があり、グローバル的にもトレードの大原則とも言える非常に重要な理論です。
株の初心者、株だけに限らずFXなどのチャート分析においても有効なのでトレーダーにはマスター必須の理論です。
下記は簡単なグランビルの法則のイメージ図です。
A~Dがグランビルの法則にもとづく買いポイントを指しています。

グランビルの法則(概要図)
まず、このイメージ図でも一目で分かるように株価は移動平均線から離れるように動き、離れたらまた近づき、そして再び離れるという動きを繰り返します。
株価は移動平均線を基準にしてバウンドするように動きます。
これがグランビルの法則による株価の挙動です。
株価が移動平均線から離れるように動く、つまりそれは株価が上昇することを意味します。
この時に大事なのは移動平均線が上向きであるということです。
上昇=値上がりです。
移動平均線付近で株を買うと株価が離れる動きを利用して必然的に値上がりが期待できる、というのがグランビルの法則の買いポイントです。
上図A~Dの4つの買いポイントの定義は次のようになります。
A:移動平均線が下降後、横ばいになるか上昇しつつある局面で、株価が移動平均線を上に突き抜ける。
株価が大底圏から反発し上昇トレンドに転じるタイミングが狙えるポイントです。
B:移動平均線が依然として上昇しているのに株価が移動平均線を下回る場合。
上昇トレンド中の押し目タイミングが狙え、再度移動平均線を抜くポイントです。
C:株価が移動平均線の上にあって、株価が移動平均線に向かって下降したものの、交差することなく再び上向きに転じる。
Bと同様に押し目のタイミングが狙えるポイントです。
D:移動平均線が下降している場合でも、株価が移動平均線と大きく乖離して下落した場合。
移動平均線まで戻る値幅が狙えるポイントです。
個々のポイントの詳細は別途解説していきますが、要はグランビルの法則に則り移動平均線の近く、それも必ず移動平均線よりも上の位置で株を買うということです。
そうすると株価が離れる距離の分だけ値幅が期待できます。
逆に株価が移動平均線から離れた位置買うと、株価が移動平均線まで戻る流れに巻き込まれてしまい損失のリスクがありますから避けましょう。
これで「移動平均線が上向きで買っても上昇トレンドがいつ終わるかわからない。 買ったとたんに下がり始めて損をする危険性もあるのでは?」というみなさんの疑問については解消したと思います。
上がってる途中で追いかけて買うのではなく、必ず移動平均線の近くで抜けている状態で買うというのが鉄則です。
先の投稿で「株価が移動平均線を抜けた瞬間に買う」と書きましたが、これはグランビルの法則のAとBのポイントを指しています。
各ポイントの詳細は以下のページで確認してください。
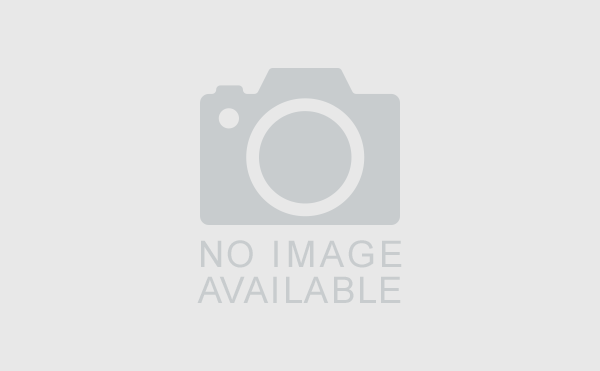
“マスター必須!グランビルの法則” に対して1件のコメントがあります。