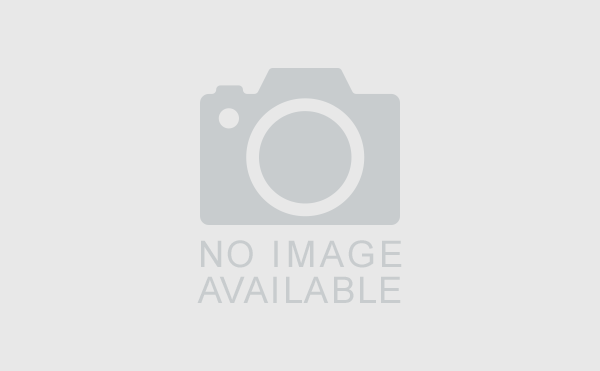移動平均線の収束抜け上昇(6545 IIF)
グランビルの法則の最初の買いシグナル
インターネット・インフィニティ(6545)の日足チャートです。

2018年5月の高値から長期トレンドラインを1月に転換した後、フラットフォーメーションを形成し、ブレイクアップして上昇に転じています。
それまでに、3本のトレンドラインが存在し(正確には4本)、それぞれは安値を更新したことで消滅しました。
現在、最安値の511円は12月ですので、最新のトレンド転換は1月下旬になります。
これまでのトレンドラインは、ファンラインとなり、4本目が真のトレンドラインになったことになります。
高値から8か月の日柄が経過し、期間的に不足はありません。
その間に、波動的にも三段下げとなりましたので、この転換は時間との相関関係も高く、妥当性の高いものとなりました。
(ここまでの経緯の詳細については、以下の18年11月6日の投稿を参照)
https://e-intelligence-e.com/?p=1756
さて、今回の上昇に至った重要なテクニカル的要素は、移動平均線の収束にあります。
以下は、25日移動平均線と75日移動平均線です。

1月25日にトレンド転換した時点では、まだ75日移動平均線の下げ角度は大きく、25日移動平均線との乖離幅もありました。
移動平均線の単線分析で見ると、トレンド転換ポイントは、25日移動平均線抜けでもありますので、グランビルの法則の買いポイントに該当します。
「移動平均線が下降後、横ばいになるか上昇しつつある局面で、株価が移動平均線を上に突き抜ける。」
しかし、通常、このように2本の移動平均線が乖離した状態では、25日移動平均線抜けの買いに対する利益確定の目標に、75日移動平均線が意識されやすいという傾向があります。
そのため、乖離幅を利益と目論む売りが75日移動平均線付近で出やすく、たとえ株価が75日移動平均線を抜けてもスムーズに上昇し難いです。
ですから、移動平均線の位置を確認せずに、単純にトレンド転換を理由に買うにはリスクが伴います。
これを解消するためには、2本の移動平均線を使った複数線分析で見ていく必要があります。
移動平均線を使う場合、最も大きな上昇の勢いが期待できるのは、複数の移動平均線が収束している局面を、株価が上抜けた瞬間です。
これをグランビルの8法則に当てはめると、移動平均線の2本共が最初の買いポイントに該当します。
「移動平均線が下降後、横ばいになるか上昇しつつある局面で、株価が移動平均線を上に突き抜ける。」
この場合、2本の移動平均線の足の長い方の移動平均線は、必ず株価と短い方の移動平均線の上に位置します。
⇒ グランビルの初動の買いポイント
⇒ グランビルの初動の買いポイントのまとめ
このポイントが、株価が大底圏から反発し上昇トレンドに転じる「初動」のタイミングです。
二番底確認後の収束抜け
インターネット・インフィニティの場合、転換後の株価は75日移動平均線を目指して上昇することなく、横ばいに推移しました。
(このように、底値圏でトレンド転換した場合、次にどのようなフォーメーションを形成するのかを、ある程度の日柄を持って見極めることが重要です。)
およそ1か月間、横ばいに推移(フラットフォーメーション)したことにより、25日移動平均線は横ばいから上向きに転じ、75日移動平均線の下げ角度も、次第に横ばいに近づき緩やかになってきました。
これにより、2本の移動平均線は互いに収束して接近し、乖離幅はほぼ無くなりました。
こうなると、75日移動平均線までの利益を狙った買いと、その買いによる利益を確定する売りは減少します。
反対に75日移動平均線抜けの上昇を目論む仕込み買いが増加してきます。
結果、フライング気味にミニ・ゴールデンクロスする手前で、株価は2本の移動平均線を抜けていく動きとなります。
(ゴールデンクロスとは、200日と75日移動平均線の関係においての呼び方です。)
これが、一般的なグランビルの法則に則った最初の買いポイントとなります。

加えて、2月安値は12月の安値を割り込みませんでしたので、二番底を確認できたことになります。
具体的な買いポイントは、1月21日高値をレジスタンスレベルラインと見立てますが、ラインの上に75日移動平均線が位置していますから、「75日移動平均線抜けが買いポイント」となります。
レジスタンスレベルラインを抜けた時点で、リバーサルフォーメーションである「ダブルボトム」が成立します。

フラットフォーメーションを形成した間に、ボリンジャーバンドはかなり収束してきました。
ボラティリティが低下し、収束は次に発散する際の大きなパワーになります。
結果、抜けた株価は大きく上昇することになりました。
安値から、ほぼ2倍に、買いポイントからも1.4倍なったことになります。
底値圏の移動平均線の収束した局面は初動候補
この銘柄と同様のチャートでも、相場の勢いが追い風となれば、収束抜けの反応に期待できます。
移動平均線が収束しつつある状態で、株価はミニゴールデンクロスを待たずに、手前で先に抜けます。
株価が抜けてからほどなく25日移動平均線は75日移動平均線の上に出ます。
そうなると「順パターン」となり、移動平均線分析の分位別図的にも上昇トレンドとなります。
その後、株価は上向きの25日移動平均線から乖離したまま上がっていきます。
日柄経過とともに上昇トレンドラインが出現しますから、トレンド割れ、もしくは25日移動平均線割れで利益確定をしたとしても、上向き角度分そのものが利益として見込めることになります。
例えば、SERIOHD(6567)なども同様です。

他にも、類似チャートの一例として、下記の銘柄が該当します。
・シャープ(6753)
・さくら(3778)
・TBS(9401)
・ウエーブロック(7940)
なお、各銘柄の利益確定ポイントは、中期的には移動平均線やトレンドライン、短期的には修正波の出現などを詳細に見て、個別に決定していきます。
当研究所では、銘柄の選定において、一般的なスクリーニングソフトは使用せずに、移動平均線の位置や角度、収束具合、ボリンジャーバンド、一目均衡表などのチャート形状をそのままインプットデータとして、全上場銘柄を対象にスクリーニングしています。
通常、スクリーニングソフトは4本値をダウンロードして、移動平均線や乖離率の算出、高値安値…を、数値計算を駆使してプログラミングし、システムを構築します。
そして、各指数に対してパラメータを操作しながらパフォーマンスを狙うことが多いですが、当研究所ではチャートそのもののをビジュアル的な形状から識別し、瞬時に対象銘柄を抽出するアプローチを採用しています。
ですから、複数の移動平均線の乖離率(収束具合)においても、単に乖離率だけを見るのではなく、そこに至るまでの日柄や、移動平均線のカーブや角度、株価との位置関係までをもパターンとして認識しています。
更に、スクリーニングした銘柄を、テクニカル理論に照らし合わせて精査し、対象銘柄としての是非を判定し、最終的な売買ポイントを確定させています。
加えて、各市場指数の騰勢を加味することで、無用なドローダウンを回避しています。
<2019年3月7日、追記>
3月7日のザラ場の日足チャートです。

昨日6日は、12月高値がレジスタンスとして意識されたことで、利益確定の売りに押されました。
現在修正波の途中ですが、短期トレンドライン付近で逆張りするか、高値の上抜けを順張りするかになります。
いずれにしても、上昇した場合の利益確定目標は、200日移動平均線となります。
<2019年3月18日、追記>
2月18日安値からエリオット波動の波1がスタートし、現在は修正波の波2のb波と思われます。
ここから切り返すと、波3となりますので、波1よりも大きな比率での上昇になりそうです。
但し、200日移動平均線付近がレジスタンスとなり利益確定が出やすくなります。