日経平均株価はインターナル・トレンドラインを(2018年12月27日)
ザラ場で下値傾向線を意識して反発したものの
NYダウの反発により日経平均株価は大きく反発しました。
先の投稿でトレンドラインの下値傾向線が、今後下げた場合に下値メドになると記載しました。
そして、25日の急落の際に、ザラ場では下値傾向線が意識され、一時的に下げ止まる動きを見せたものの、下値傾向線を割り込んで引けました。
以下は12月25日の日足チャートです。
右がザラ場のチャートですが、当初のイメージ通りに下ヒゲがタッチして切り返しています。

ここから反発かと思われましたが、下値傾向線がサポートとして機能することなく崩れ、株価は下値傾向線を割り込んで引けました。
インターナル・トレンドラインの存在
以下は27日引け後の日足チャートです。
下値傾向線を割り込んだ後、26日夜にNYダウが切り返したことにより、最終的には18,948円が下値となり27日は反発しました。
但し、この下値は現時点でのことで、底値と決まったわけではありません。

さて、何故下値が18,948円であったのか。
上記チャートは10月2日高値を起点に、12月3日高値を通過するラインをトレンドラインとしています。
これが正規のトレンドラインです。
10月、11月の動きを振り返ると、11月8日高値をレジスタンスレベルラインとしてフラットに推移していた株価は、日経225先物の日中・夜間ともに、12月3日に窓を空けて一瞬飛び出した直後に下落しています。
上昇局面入りと思わせる「ダマシ」となった足です。
(ファンダメンタル的には、相場上昇を阻んでいた米中貿易摩擦に解消の兆しが見えたことが要因です)
この、ダマシとなった乖離的なろうそく足を除外して、インターナル・トレンドラインとして引き直してみます。
そして、その下値傾向線を10月26日安値に合わせたのが以下のチャートです。

このインターナル・トレンドラインが、今回の局面において下値傾向線を導出するトレンドラインとして認識されたました。
上記添付の25日のザラ場チャートの様に、正規のトレンドラインも下値傾向線が意識される動きであったことから、下値を見極める分析基準が分かれたと思われます。
※ 下値メドを導出し、買い注文を出す価格をプログラムに与える場合、分散している個々のシステム上で算出するのではなく、ホスト的なシステムで処理した結果を、個々のシステムに配信します。
ホスト側のプログラムは常に更改されており、処理は一元化しておく必要があるからです。
特に、主となるトレードシステムがライセンス供与されていると、クライアント側になる方は分析機能を持たないことが多いからです。
そして、決められた価格で膨大な買い注文を集中させて、日経平均株価でさえも支配することが出来ます。
今回は、急激に大きな値幅で動いたので、他のホストとの連動が遅れて、ポイントをブレさせたようです。
一目均衡表のN波動
10月の最高値からここまでの動きを、一目均衡表の波動論の観点から見てみます。
以下のチャートのラインAは10月2日高値と10月26日安値を、単純に結んだ下げラインです。

ラインBは戻りの上げラインです。
そして、ラインCはラインAを単純にコピーして、戻り高値を起点に置いたラインです。
コピーなのでラインの長さ、角度は全く同じです。
波動の形から、一目均衡表の「N波動」であることが確認できます。
また、ラインの到達点は、ほぼ今回の下落の安値になり、基本計算値からもは「N計算値」と合致します。
さて、ここで更に仮説として注目したいのは、ラインCの到達点が27日の位置にあることです。
このチャートに上記の正規のトレンドラインを重ねたものが、下記のチャートです。

ラインCの到達価格と、正規のトレンドラインに対する下値傾向線の価格が同じになります。
このことから、もし25日の下げが想定以上の急落とならなければ、当初の分析通りに株価が下値傾向線に到達するのは、27日になっていたのかもしれません。
もし、そうだとすると、インターナル・トレンドラインを持ち出すことなく、27日に正規の下値傾向線に下ヒゲがタッチする、綺麗なチャートが描かれたのではないかと考えられます。
(但し、N計算値の価格は、必ずしも計算通りにはなりませんが)
加えて、一目均衡表の受動的波動における時間的観点の「対等数値」の考え方にも合致しています。
エリオット波動からの戻り高値のメド
10月2日高値からの下落をエリオット波動で分析してみます。

10月以降の下げを下降のインパルス・パターンと想定します。
波1のインパルス・ウエーブ、波2のコレクティブ・ウエーブ、そして波3のインパルス・ウエーブが完成し、現在は波4のコレクティブ・ウエーブの形成途中とカウントすることが出来ます。
もし、今の上昇が波4だとすると、その戻り高値のメドは波1の安値となります。
エリオット波動のインパルス・ウエーブにおけるルールは以下の3つです。
1.波2は波1の始点を割り込まない。
2.波1、波3、波5の中で波3が一番小さくなることはない。
3.波4は波1に重ならない
3つ目のルールから、波1の安値は20,971円であることから、戻り高値はこの価格よりも下で終わることになります。
なお、波1の安値以下に上記トレンドライン、またはインターナル・トレンドラインが位置する状況となれば、これらのラインがレジスタンスとして機能しますので、戻り高値のメドとなる可能性があります。
恐らく、ラインの方がレジスタンス機能は高いと思われます。
また、波3は波1と同じ値幅になっています。
「波の均等性」と言うエリオット波動の観点から、波1、波3、波5のうちいずれか2つの波が変化率の点でも、時間的長さの点でも同程度になりやすいという習性があります。
通常は波3が最も大きくなる傾向がありますが、波3は波1と同じ普通の波となっています。
「波の延長」の観点から、次のインパルス・ウエーブとなる波5は延長して巨大化しやすいという習性から、大きな下落となるという法則があります。
このことから、波4の戻りの次に来る波5は相当大きな下落になる可能性が高いので注意が必要です。
波4がいくらの価格まで戻るのかは分かりませんが、波5の開始点は波4のトレンド転換が兆候として重要なポイントになります。
波4のリバウンドが終わり、再度波5が安値を目指す動きとなった場合、正規のトレンドラインだけではなく、インターナル・トレンドラインの下値傾向線も、波5の安値メドとして意識しておく必要性があります。
<急落前の安値メドについて>
<2018年12月29日、追記>
12月3日のろうそく足を除外して、インターナル・トレンドラインとして引く手法は、個別銘柄でも見受けられます。
また、同様に12月25日の急落を除外して引くラインも、今後出てくると思われます。
大統領選挙でトランプ勝利が濃厚となり、日経平均株価が急落した際のろうそく足も除外して分析すると、多くのケースで整合性が取れます。
以下は清水建設のチャートです。
12月3日、12月25日の除外するサンプルチャートです。

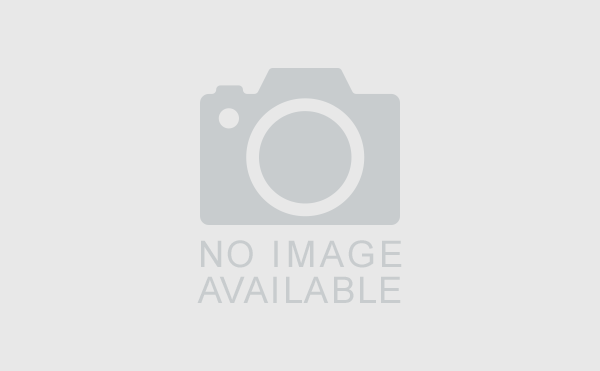
“日経平均株価はインターナル・トレンドラインを(2018年12月27日)” に対して2件のコメントがあります。