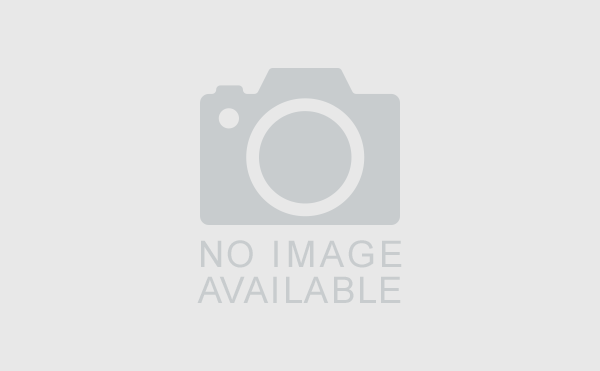今後の日経平均株価のゆくえ
今後の日経平均株価のゆくえ
日本経済新聞的分析
これから日経平均株価はどちらに動くのか?
株価が動く方向には、①上昇、②下降、そしてどちらでもない③横ばいの3方向があります。
下記の記事は2018年8月9日の日本経済新聞朝刊のコピーです。
記事の主旨としては、日経平均株価の長期線(200日移動平均線)と中期線(75日移動平均線)、そして短期線(25日移動平均線)が収束してきているので、近い将来に相場が大きく動く兆候を示しているとし、過去2年間においても同様の現象が起こったので、今回も上昇方向に大きく動くのではないか?というものです。
2016年と17年の2回、移動平均線3線が収束する現象が起きています。
記事のチャート図からもその後の株価が上昇したので今回も上昇するのではないかという見解です。
そして記事では日米の政治経済情報も絡めて説明しています。

テクニカル分析による株価の今後のゆくえ
さて、これをテクニカル分析の観点から説明してみましょう。
以下に記事と同じ期間で2018年8月10日現在の詳細な日経平均株価のチャートを添付します。

1.移動平均線
まず、大きなトレンドで日経平均株価を見ると、長期の移動平均線(赤色)である200日移動平均線は2016年11月より上昇に転じています。
長期的視点では約22か月間上昇し、そのトレンドは現在も継続中です。
次に中期の移動平均線である75日移動平均線(緑色)は、200日移動平均線に対して収束と発散を繰り返しながら2018年6月頃より上昇に転じています。
2018年8月10日現在では僅かではありますが上昇は継続しています。
しかし、次営業日(8月13日)以降に株価が今よりも下落すると、応答水準を下回ることになり75日移動平均線は下向きに方向転換をすることになります。
最後に短期の25日移動平均線(青色)は75日移動平均線に対して収束と発散を繰り返しながら7月下旬より上昇に転じ、現在も上昇中です。
応答水準までは少し値幅がありますから大幅な下落がない限り上昇、もしくは横ばい継続です。
このことから現在の日経平均株価は長中期的にも短期的にも上昇中であることがわかります。
そして、長期、中期、短期の移動平均線は互いに接近して収束しています。
移動平均線の分位別株価的には、下から長期線、中期線、短期線の順になり3線ともに上昇中にあることから順パターンとなります。
このように移動平均線が収束した状態は、株価の煮詰まり感を示唆し近く保ち合い放れの転機が訪れる兆候といえます。
今後、株価が3本の移動平均線を上抜ければ上昇トレンドが継続する可能性が高いとみられます。
上昇トレンドが継続するならば、押し目買いが有効な局面です。
目線としては、グランビルの法則Bのパターンで再度株価が移動平均線を抜ければ買いポイントとなります。
この場合の絶対条件は株価が3線をともに上回ることです。
(理由については「移動平均線の重要な役割(レジスタンスライン)」を参照)
2.サイクルと波動
さて、視点を替えて波動という観点から見た場合、200日移動平均線に対して株価は3段上げを達成しています。
3段上げ3段下げの法則からすると長期的に株価は高値圏に位置しているとも見られます。
株価が収束した移動平均線を上抜ければ上昇継続ですが、もし収束した移動平均線を割り込めば下げへの転換を意味し、株価は急落するという可能性を秘めています。
移動平均線が収束している局面は上放れの局面でもありますが、裏を返すと下放れをする局面でもあり、買い方からすると非常に大きなリスクをはらんだ局面であるということを意識しておくことが重要です。
ここは正にグランビルの法則の売りポイントです。
売りが加速し急落する局面でもあります。
買いが否定され空売りを仕掛けるポイントとなります。
3.フォーメーション
さらに、ラインを引くことで上昇・下降のレジスタンス・サポートポイントをより明確に見極めることが可能となります。
2018年1月高値から3月の安値までの値幅に対して、5月の戻り高値は約70%となりエリオット波動のフラット・コレクションと想定されましたが、7月に5月の22,000円付近のサポートレベルラインを割り込んだことにより、ジグザグ・コレクションと変化しました。
レジスタンスラインとサポートラインを引くことでチャートの形を識別しやすくなります。
分析期間の長さによりフォーメーションは2種類の見方が出来ます。
<シンメトリカルトライアングル>
下記のチャートは、2018年1月高値を起点とするレジスタンスラインと、2016年6月安値を起点とするサポートラインを引いたチャートです。
200日移動平均線をベースにした長期のフォーメーションで、シンメトリカルトラインアングルを形成しています。
波動・サイクル的観点からはリバーサルフォーメーションになり、2016年6月からのサポートラインはトレンドラインですので割り込むと長期の上昇トレンドが終焉することになります。

<アセンディングトライアングル>
2018年5月を起点とした水平のレジスタンスラインと、3月を起点としたサポートラインによってもトライングルが形成されます。
レジスタンスラインはほぼ水平で安値を切り上げるアセンディングトライアングルです。
若干高値が切り下がりシンメトリカルトライングルの様にも見受けられますが、株価23,000円を意識した水平のレジスタンスラインと判断しても差し支えないでしょう。
1月からの下落を下降と見るならば「弱気相場の上昇ホリゾンタル」となります。
逆に4月からを上昇と見るならば「強気相場の上昇ホリゾンタル」となります。

いずれにしても、現在株価は収束した3本の移動平均線を既に割り込んでいます。
どちらのフォーメーションにしても今後の株価は、
① どちらかのサポートラインで止まり、再び保ち合い継続となるか
② サポートラインを割り込み下落に転じるか
あるいは、3本の移動平均線を上抜けた後に、
③ レジスタンスラインを突破し再上昇となるか
この3パターンとなり来週は注目される局面となるのが必至です。
③の実現後、最終的には2018年5月21日高値から引くレジスタンスレベルライン(23,051円)を超えてくると本格的な上昇に転じると判断できます。
上昇に転じる場合は、レジスタンスレベルラインは非常に重要な観点ですので常に意識しておく必要があります。
逆に下降に転じる場合は、長期のトレンドラインを注視し、3月、7月を起点とするサポートレベルラインが意識されることになります。
なお、トライアングルの終点はラインがクロスするポイントですので、それまでに結論は出ます。
加えて、レジスタンスレベルライン付近にはボリンジャーバンド+2σが位置していますので、逆張りポイントであることも視野に入れると良さそうです。
株価がレジスタンスレベルラインを抜けると、当然のことながらボリンジャーバンドは発散しますのでトレンドフォローのスタンスとなります。
反対に、7月安値のサポートレベルラインと割り込むことになると、収束したボリンジャーバンド-2σを突破すると、ボリンジャーバンドが拡散する局面となりますので逆張りによる買いはご法度です。
併せて一目均衡表の雲も抵抗帯として位置していますので注意が必要です。

※ トルコショックによるリラの急落は8月13日以降の相場に少なからず影響し、週明けの日経平均株価は先週末比で大きく下落して始まると予測されます。
商いが薄い夏休みと重なり乱高下しそうですが、新たなテクニカルポイントの出現に注意を払う必要があります。
<以上、2018年8月12日記載>