Ⅴ-2-2.移動平均線による分析
Ⅴ-2-2.移動平均線による分析
1. 単線分析
現値線とその移動平均線を使って株価の方向性を探るものである。
移動平均線は株価の移動平均値を使うことから日々の株価のばらつきが平準化され、株価そのものより移動平均線の方が方向を探りやすくなる。
また、移動平均線にはその計算から慣性の力があり、株価が移動平均線から一時的に乖離しても移動平均線に引き戻される力が働く。
つまり、移動平均線が上向いているなら株価の方向性は上昇をたどることが予想され、その反対なら株価は下降をたどると予想される。
しかし、株価が急落する場合に、移動平均線が遅れて下方転換するという悩ましい事実がある。一方、上方転換は株価の上昇にある程度追随するケースが多い。
従って、株価が急落する際、単に移動平均線の方向転換のみの判断に頼ることは危険を伴う。
注目しておきたいのは、移動平均線の上方、下方転換の前兆として、株価が移動平均線を上回る、あるいは下回るというシグナルが出現することだ。
そうした前兆が出現した場合、移動平均線が方向転換するまでどのように身構え、対処するかがポイントとなる。その際に理解しておかねばならないのが「応答水準」の考え方である。
2. 応答水準について
応答水準: 応当日の株価。
応当日とは、当日から当日を含めたn日前の日付のこと。
翌日の株価が応当日の株価より高ければn日移動平均値は高くなる。逆に翌日の株価がその応当日の株価より安ければn日移動平均値は低くなる。
つまり、翌日の株価とその応当日の株価を比べることによって移動平均線の方向が予測できる。
翌日の株価は分からないが、その応答水準は分かっており、急騰や急落でもない限り応答水準との高安関係は変わりにくい。
このことを応用すれば翌日の応答水準から逆算して、翌日のザラバ株価の推移から移動平均線の方向性がある程度予測でき、株価の方向性も見当がつきやすくなる。
3. グランビルの考え方
① 相場の語っていることの代わりに、他人の言うことに耳を傾けること
② 耳寄りなニュースで株式を買うこと
③ 空売り株数の減少している株式を買うこと
④ 天井値と大底値を当て推量すること
⑤ 個人的な推測に基づいて、強気にくみし続けること
⑥ 不本意な取引をすること
⑦ 技術的な指標を無視すること
⑧ 市場に長居しずぎること
⑨ 配当の重要性にとらわれて、目が利かなくなること
⑩ 基本的な指標にこだわりすぎること
「タイミングこそ全てである」とし、株式相場の基調的(ファンダメンタルズ)な変動よりも、技術的(テクニカル)な変動を重視することと述べている。
4. グランビルの8法則
買いシグナル:
① 移動平均線が下降後、横ばいになるか上昇しつつある局面で、株価が移動平均線を上に突き抜ける。
② 移動平均線が依然として上昇しているのに株価が移動平均線を下回る場合。
③ 株価が移動平均線の上にあって、株価が移動平均線に向かって下降したものの、交差することなく再び上向きに転じる。
④ 移動平均線が下降している場合でも、株価が移動平均線と大きく乖離して下落した場合。
売りシグナル:
⑤ 移動平均線が上昇後、横ばいになるか下落しつつある時、株価が移動平均線を下に突き抜ける。
⑥ 移動平均線が依然として下降しているのに、株価が移動平均線を上回る場合。
⑦ 株価が下降する移動平均線の下にあって、移動平均線に向かって上昇し、交差しないで再び下向きに転じる。
⑧ 移動平均線が上昇している場合でも、株価が移動平均線とかけ離れて大きく上昇した場合。
※ ④の反発は弱い。しかも、戻りのほんのわずかの時間であり、多くの人がその戻りで売り損なう可能性が高い。買いは株価が上昇トレンドへ転換してからが基本である。
5.複数線分析
現値線と2つの移動平均線、あるいは3つの移動平均線を使う分析方法である。
日足の場合は、25日、75日、200日。
週足の場合は、13週、26週、52週。
月足の場合は、12か月、24か月、60か月。
5. 順パターンと逆順パターン
順パターン: 短期線と長期線がともに上昇中にあるパターンで、強いトレンド中にあることを示す。特に両線が発散中にあるときは、さらに強い上昇の勢いがある。よって、このパターンを形成しているときは押し目買いが有効な局面となる。
株価と各線の位置は上から現値線、短期線、長期線と順に並んでいる。
逆順パターン: 短期線と長期線がともに下降中にあるパターン。株価は強い下降トレンド中にあり戻り売り相場となる。
株価と各線の位置は低い方から現値線、短期線、長期線となる。
移動平均線の収束と発散
2つの移動平均線の短期線と長期線が互いに接近して収束する場合は、株価の煮詰まり感を示唆し、近く保ち合い放れの転機が訪れる前兆とも言える。
発散は2つの移動平均線が互いに離れて広がる様子である。
これは順パターンの局面で株価の上昇が最も強い場面を示唆する。逆順パターンの局面では、株価の下落の勢いが最も強い場面を示唆する。
移動平均線と株価の位置関係
株価が時計回りに循環する局面で短期線と長期線の2本の移動平均線と株価の位置関係を「移動平均線と株価の分位別株価」と言う。
6通りの局面を並べると株価のボトムからピークへ、そして再びボトムへ時計回りのように相場の循環行程が非常に分かりやすい図を描くことができる。
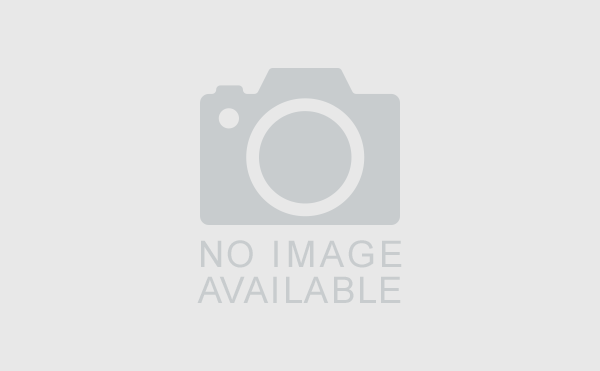
“Ⅴ-2-2.移動平均線による分析” に対して3件のコメントがあります。