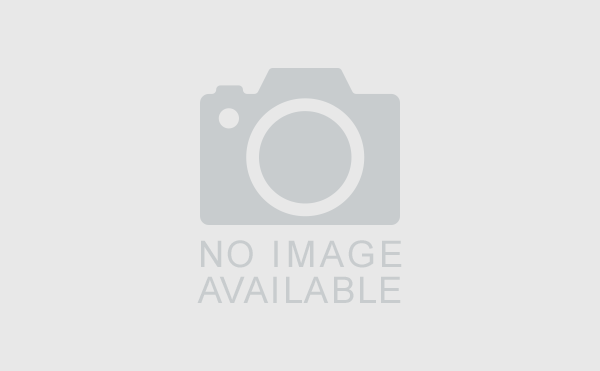グランビルの法則Aパターンのダマシを見抜く事例(2183 リニカル)
意識されている移動平均線を抜ける瞬間を狙う!
グランビルの法則Aパターンで急騰した事例をケーススタディとしてご紹介しますが、ベースとなる移動平均線の見極め方についてお話します。
下図は” 2183 リニカル ”の2016年9月頃の株価チャートです。

前回Aポイントで急騰した ” 3936 グローバルウェイ ”をケーススタディとしてご紹介しました。
グランビルのAポイントを復習しますと、
A:移動平均線が下降後、横ばいになるか上昇しつつある局面で、株価が移動平均線を上に突き抜ける。
その際の着目点として移動平均線を抜ける直前の株価は概ね横ばい傾向であることが好ましいとお話ししました。
理由は、株価が横ばいに推移しているこの期間に株を買った人からする移動平均線まで株価が到達してもほぼ利益が出ていないので、少しぐらい上昇したとしても売られ難い状態にあるからです。
株価が抜けた瞬間に流入する資金の勢いを邪魔することがないので「移動平均線を抜ける直前の株価は概ね横ばい傾向」であること、これが非常に重要な着目点です
さて、リニカルの場合はどうでしょうか?
株価チャートから急騰する前までの動き(赤丸の直前)を見ると25日移動平均線がなんとなく意識されていることが分かると思います。
概ね25日移動平均線に沿って株価は推移していました。
そして赤い丸の25日移動平均線抜けで反応しました、
急騰した株価は75日移動平均線が利益確定の目標となり一相場が終わっています。
4日間で15%の利益です。
急騰直前の約3週間の株価はほぼ横ばいに推移しています。
特に直前1週間はほとんど動かずに推移しています。
横ばいに推移することで緩やかに下降してきた25日移動平均線と合流し大きなパワー(資金)をかけることなく抜けていきました。
この動きがググランビルの法則Aパターンを狙う場合の理想的な株価の推移です。
株価の推移を観察しダマシを見抜く
それに対して急騰する前の期間をよく観察すると、何回か25日移動平均線を抜けたものの押し戻されて再び割り込む動きとなっています。
「移動平均線を抜けたら買い」というグランビルの法則が成立していません。
この理由は何でしょうか?
理由は抜ける直前の株価の動きにあります。
株価チャートの左半分付近で25日移動平均線を抜ける前の数日間は比較的大きめの陽線で株価は上昇しています。
大きめの陽線が出るとそのだけでも上げた値幅は大きいので、心理的にも「儲かった感」が大きくなります。
つまり短期目線のトレーダーからすると多少なりとも利益が乗ったので早めに利益確定をして手仕舞いたいと考えて25日移動平均線を利益確定の目標にしてきたのです。
これに対して25日移動平均線を抜けたら買うというスタンスのトレーダーもいますから、ここに需要と供給の戦いが起こります。
これがリスクです。
結果、「供給 > 需要」となり株価は25日移動平均線を抜けたものの利益確定に押されて下落する動きとなったのです。
このような状況で「移動平均線を抜けたら買い」というグランビルの法則Aパターンは否定される現象が起きました。
「移動平均線を抜ける直前の株価は概ね横ばい傾向」
いかに大切な着目点であるかということを分かって頂けたと思います。
ちなみに、このように「抜けたら買い」という理論があるにも関わらず、そうならなかった現象のことを「ダマシ」と表現します。
「移動を抜けたから買ったのに下がってしまった…、ダマシにあってしまった…、チャートにダマされた」という使い方をします。
トレードにおいてダマシはつきものです。
いかにダマシを見抜いて回避するかが重要になってきます。
「移動平均線を抜ける直前の株価は概ね横ばい傾向」、この着目点はダマシのリスクを回避する意味でも非常に意味がありますので、グランビルの法則Aパターンの場合は売買基準にする移動平均線を抜ける直前の株価の推移状態をよく観察することが重要です。
参加者の損益状況や心理状態を分析することで無駄なリスクを回避することが可能になります。
リスク = 損失(ダマシ)の可能性
その一つの着目点として、移動平均線を抜ける直前の株価は概ね横ばいの方が良いということで説明してきました。
逆の言い方をすると二本の移動平均線の乖離幅を利益にするトレード手法もあるということです。
具体的には後日説明しますが、移動平均線が支持抵抗として機能するという原理原則さえマスターしておけば誰にでも使える手法です。
まずは移動平均線と株価の関係における需要と供給について押さえてください。