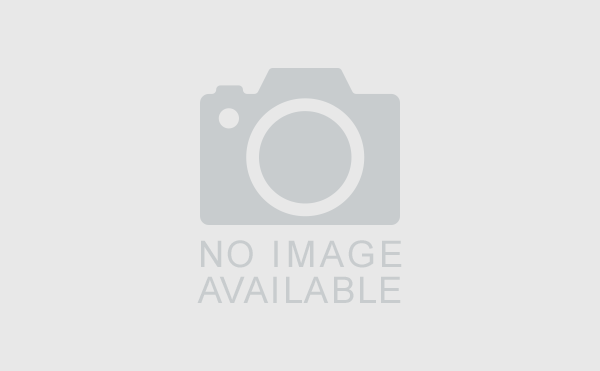Ⅵ-2-1.信用取引
Ⅵ-2.信用取引
Ⅵ-2-1.信用取引
1.貸借倍率
貸借倍率: 買い残÷売り残
(買い残が売り残に対してどの程度(何倍)積み上がっているかを表したもの。
6か月以内の決済。売り買いの需給。
買い残は将来の売り圧力、売り残は将来の買い圧力。
しかし、売り残の場合には機関投資家が何らかの理由から現物取引で売却できない場合、信用売り(ツナギ売り)で売却して損益を確定させ、その後の保有している株券を渡すことで決済される例も少なくない(現渡し)。
貸借倍率は、市場残高の場合は、金額、株数ベースで算出できるが、個別銘柄の場合はディスクローズされているのが株数のみであり、貸借倍率も株数ベースのみでしか算出できない。
2.評価損益率
信用買い建玉残高の中で評価益と評価損を合算して全体での損益がどのようになっているかを算出したもの。
東京証券取引所からは個別銘柄および市場全体での評価損益率は発表されていない。
評価損益率は通常買い残について推計しており、売り残については推計していない。
もともと売り残の規模は買い残の規模と比較して少ないことや、推計するデータがないこと、さらに売り残にはツナギ売りが含まれ、現渡しで決済されるケースも多いことから評価損益があまり気にされない面もあるためだ。
評価損益率は、-10%を上回ると過熱感が台頭、-20%を下回るとボトム感が台頭してくる。
信用取引は短期の売買が中心であり、残っている建玉には評価損を出しているものが多く含まれ、評価損益率がマイナスであるのが通常の状態であるためだ。逆にプラスになる状態は極めて珍しい。
信用取引では買値から20%以上下落すると追証がかかる状態となり、証拠金を差し入れるか手仕舞うかの選択になるので、評価損率-20%が1つの分岐点になる。
大勢的なピークとボトムを示すものではなく、短中期的なピークとボトムを見る上で有用。
3.空売り比率
東証の取引金額のうち、空売りの取引がどの程度あったかを金額の比率で表したものである。
ただし、空売り比率は新規の空売りの取引を対象にしたものであり、買い残のように未決済の株式の残高を表しているのではない。
空売り取引は「価格規制あり」と「価格規制なし」の2種類がある。
「価格規制あり」は内外の投資家が貸借市場で調達した株式を売却した場合と、信用取引で50単位を超える株式を売却した場合の取引である。ヘッジファンドなどの内外機関投資家の商い。
「価格規制なし」は個人投資家の行う50単位以下の信用取引のことである。小口の個人投資家の商い。
空売り比率を見る場合、「価格規制あり」と「価格規制なし」に分けた比率をみることが重要である。
市場に与える影響としてはヘッジファンドの商いが含まれる「価格規制あり」の方が大きいと考えられる。