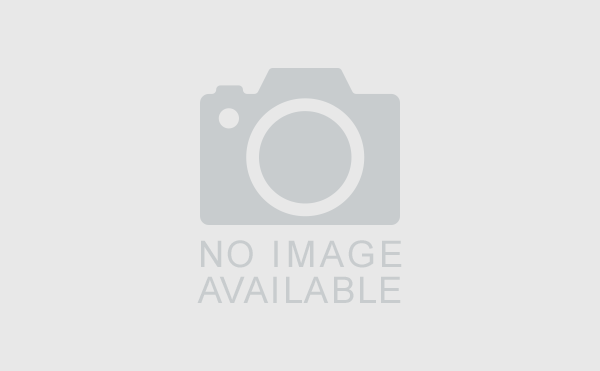Ⅴ-6―2.ストキャスティクス
Ⅴ-6―2.ストキャスティクス
ストキャスティクオシレーターという呼び名が一般的、日本ではストキャスティクス。
オリジナルの手法をファストストキャスティクオシーレターと呼び、新しい手法はオリジナルよりも遅行することからスローストキャスティクオシレーターと呼んで区別している。
日本ではスローストキャスティックオシレータの2本線を%D、slow%Dと呼ぶことが多い。
また、日本では単にストキャスティクスという場合、スローストキャスティクスを指していることが多く、オリジナルの方をファストストキャスティックと呼んで区別している。
1.計算式
%Kの計算式が、ストキャスティックスの考え方を示す最も重要な式といえる。
%K
%D: %Kを平準化したもので%Kの3日移動平均に似ている。相関関係0.999
slow%D
2.ストキャスティクスの意味
%Kは、当日の終値の位置が直近一定期間の高値と安値の間で、どの程度の位置にあるかを%で表示している。
株価の上昇局面では100%に向かい、下降局面で0%向かう。しかし、これらの推移は長期にわたることはなく、反転接近のシグナルとなる。
また、株価が反転に転じる時は%Kもピークアウトし、反発する時はボトムアウトする。
従って、株価と%Kの推移を観察することによって、両者の整合的な動きに変化が生じたときに、将来株価の変化の兆しを推察することができる。
3.採用期間のパラメータについて
計算に用いるn期間は任意に定めるが、期間を短くすれば%Kは短期の上下動を捉えることができ、期間を長くすればより長期の波動をつかむことができる。
期間に応じて売買シグナルの発生頻度が増減するので、利用者の投資期間に合わせて調整するのが良い。
4. ストキャスティクスの見方
① 指標の水準
%K、%D、slow%D共に、0%~100%の間で往復する推移を繰り返している。
0%であれば当日終値が期間最安値と同値であり、反対に100%であれば当日終値が期間最高値と同値であることから、0%に近い水準であれば売られ過ぎであり、早晩反発が近いことが期待され、100%に近い水準であれば買われ過ぎであり、早晩反落が近いことが警戒される。
一般的には20~30%以下であれば売られ過ぎ、70~80%以上であれば買われ過ぎと判断する。
指標が売られ過ぎの判断基準を割り込んだ後、反騰に転じて同水準を上回ってきたタイミングを買いシグナルとし、指標が買われ過ぎの判断基準を超えた後、反落に転じて同水準を割り込んできたタイミングを売りシグナルとする。
これらのシグナルは、%K、%D、slow%Dの順に発信されるので、ファストストキャスティックスでは%Dが%Kの確認指標となり、スローストキャスティックスではslow%Dが%Dの確認指標となる。
特に%Kについてはダマシが多く発生するので、%Kのシグナルはむしろ注意喚起と捉え、%Dでシグナルを確認するのが良策とみられる。
② 2本の線の交差
売られ過ぎ水準以下の領域で、ファストストキャスティクスでは%Kが%Dを、スローストキャスティックスでは%Dがslow%Dを、それぞれ下から上に突き抜けるタイミングを買いシグナルとする。
なお、%Kとslow%Dの組み合わせで判断することは通常行わない。
③ ダイバージェンス
価格のトレンドとストキャスティックスの推移が逆行することに注目する方法である。
具体的には、価格が安値を更新しつつある時に、売られ過ぎ水準以下で推移している%K、%Dあるいはslow%Dが下値を切り上げる動きを見せる時、価格が近く反転上昇する兆しと捉える。
この状態を、「強気のダイバージェンス」、もしくは「ポジティヴダイバージェンス」という。
逆に、価格が高値を更新しつつある時に、買われ過ぎ水準以上で推移している%D、%K、slow%Dが上値を切り下げる動きを見せる時、価格が近く反落する兆しと捉える。
この状態を、「弱気のダイバージェンス」、もしくは「ネガティヴダイバージェンス」という。
ダイバージェンスは、長く続いていた上昇相場で騰勢が鈍化した場合や、長く続いていた下降相場で下落ペースが鈍化した場合に、必然的に発生する。
5. その他の注意点
利用する際には、長い期間のデータを用いて入念なバックテストを行い、最適なnを求めると共に、ダマシの発生頻度を確認することが肝要である。