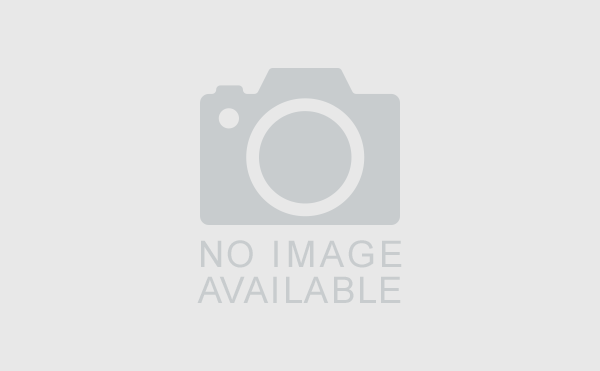Ⅴ-6-1.RSI(相対力指数)
Ⅴ-6.オシレーター分析
Ⅴ-6―1.RSI(相対力指数)
米国、J.ワイルダー
一定期間の日々の前日比騰落幅(絶対値)の合計の中で、前日比で上昇した値幅の合計がどれだけの割合になっているかを示す。
終値を連続して切り下げれば0%になり、連続して切り上げれば100%になる。0~100の間で推移する。
0%に近いと売られすぎ、100%に近いと買われ過ぎ。
ただし、連続して前日比で上昇し続けたり、下落するような展開となる可能性が小さいことを前提としており、RSIの弱点の原因ともなっている。
RSI=(n日間の前日比で上昇した日の前日比上昇幅の合計(u,n)÷((u,n)+(d,n))×100
計算式の期間nは日足では9日や14日、週足では9週。
期間を短くすればRSIは短期の上下動を捉えて発生頻度が高くなり、かつ頻繁に0と100を往復する。
一方、期間を長くすればより長期波動を捉えられるようになる半面、0や100に接近しにくくなり、50近くを推移するようになる。
1.売買判断の水準
① 高値警戒圏は株価指数で70%以上、個別銘柄で80%以上。安値警戒圏は30%、20%以下とするのが一般的な判断基準。
だが、厳密には長期のヒストリカルデータに基づく確率分析から、分析対象ごとに売買判断基準を導き出すことが望ましい。
② 売買判断をゾーンではなく、ゾーンから抜け出すタイミングを売買判断とする考え方がある。
指数の場合は30%以下の安値警戒圏から30%を上回る時点で買い判断とする、70%を下回る時点で売り判断とする。
③ 50%を基準とする考え方
RSIの50%は相場の強弱の節目とし50%以上は強気相場、以下は弱気相場。
上昇トレンドにある時は50%以上に位置すると考え、上昇トレンドにある時は40%~50%ゾーンを押し目狙いの買い場と考え、下降トレンドであれば50%~60%の間を戻り売りゾーンとする判断方法。
2. トレンドやフォーメーション分析の応用
RSIのチャートにトレンドライン分析やフォーメーション分析を使って株価の反転ポイントを探る方法。
3. ダイバージェンスの発生
株価のトレンドとRSIのトレンドが逆行(ダイバージェンス)することに注目する方法。
強気のダイバージェンス(発散)、ポジティヴダイバージェンス:
株価が安値を更新しつつある時に、低水準のRSIが下値を切り上げてくる。
弱気のダイバージェンス(収束)、ネガティヴダイバージェンス: (コンバージェンス)
株価が高値を更新しつつある時に、高水準のRSIが高値を切り下げてくる。
但し、相場が中段持ち合いに入る時にもしばしば現れる。必ずしも反転につながるという判断は危険である。
4. RSIのリスクについて
売られ過ぎ水準をまたぐ買いシグナルを連発したり、反対に買われ過ぎ水準をまたぐ売りシグナルを連発したり、ダマシが発生する。
RSIの計算上、前日比騰落合計の絶対水準の大小は考慮されない。
つまり、小動きの相場でもRSIが大きい値となる場合があり、乱高下する相場でもRSIが小さい値となる場合がある。従って、RSIを使用する場合には、常にトレンド系指標などと対比しながら投資の適否を考える必要がある。
RSIは利用できる場面と利用できない場面がある。