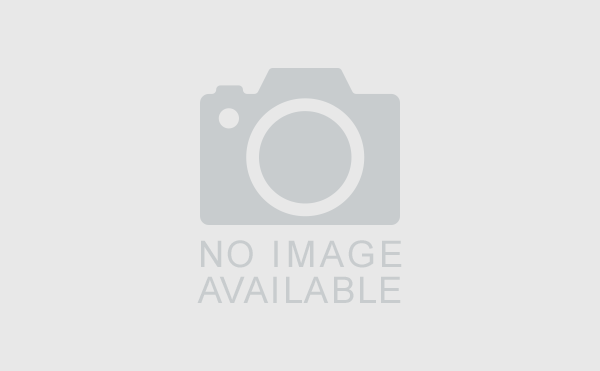Ⅱ-4-5.GDPデフレター
Ⅱ-4-5.GDPデフレーター
デフレーター: 内閣府が四半期で公表するGDP統計の一部で、元々名目GDPから実質GDPを算出するために用いられるものであるが、名目GDP/実質GDPという性格から見れば経済全体の物価動向を総合的に示す物価指数である。
一般によく知られる物価指数に消費者物価指数(CPI)などがあるが、これは消費者の購入している財・サービスの価格が調査の対象となっている。
これに対してGDPデフレーターは消費者(家計)だけでなく政府の公共投資や企業の設備投資などにかかる部分も含まれてり、その点で日本経済の総合的な物価動向を表す指標となっている。
名目GDPを実質GDPで割ることによって結果的に算出される。
計算方法
1. インプリシット・デフレーター
2. パーシェ方式
3. 連鎖方式
4. コモディティ・フロー法
利用上の注意点
輸入品価格の上昇は、GDPデフレーターの下落要因であること、またその輸入品が中間需要に向けられる割合により影響の大きさが異なることに注意が必要である。
輸入原材料価格の上昇は、輸入はGDPの控除項目であることから名目付加価値の減少(実質付加価値はそのまま)をもたらし、GDPデフレーターを低下させることになる。
これが第1次的なGDPデフレーターへの影響である。
第2次的にこの名目付加価値の減少を回復すべく製品価格の上昇(価格転嫁等)という判断がおこなわれればGDPデフレーターは上昇し、いわゆるホームメードインフレとなる。
近年の物価下落の要因として、新興国からの安い衣料品、家電製品、雑貨等の流入が指摘されるが、これは消費者物価指数に対しては正しいが、GDPデフレーターについては必ずしも正しくないことに注意が必要である。
安い輸入消費財の流入は前述と逆の理由から名目付加価値を増加させるので第1次的にはGDPデフレーターの上昇要因となる。
ただし、安い輸入消費財と競合する国産品価格の下落という判断がGDPデフレーターを低下させることになる。
このように輸入物価の変動が早く反映される国内企業物価指数(CGPI)や消費者物価指数(CPI)に比べると感覚的にはなじみにくい面があるほか、四半期ごとに公表されるので速報性については劣っている。