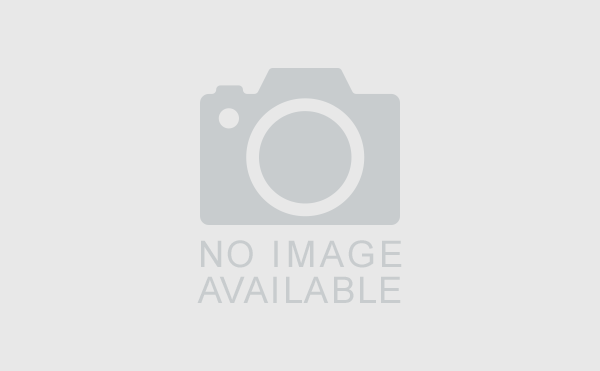Ⅱ-4-4.デフレーションとディスインフレーション
Ⅱ-4-4.デフレーションとディスインフレーション
デフレーション: 一般物価水準の継続的下落と定義され貨幣価値の上昇をもたらす。
内閣府では2年以上の継続的物価下落をデフレと便宜的に定義している。
ディスインフレーション: 物価上昇率が低下すること、すなわち物価は上昇するものの大きくは上昇しなくなる、またはしていない場合。
デフレになった場合、経済的弱者の失業を促進させる方が経済全般へのダメージが大きいことからインフレよりもデフレの方が社会全体への害が大きい可能性がある。
1. デフレーションの影響
① メリットを受ける例
物価下落またはその予測により実質金利(=名目金利―インフレ期待)が上昇するため、同額の名目利子の受け取りがあった場合は実質価値が上昇する。
物価の下落により実質的な生活水準が向上する。また国債など債権の保有者は市中金利の低下による債券価格の上昇で営利を得る。
② デメリットを受ける例
住宅ローンなどで債務を抱える場合は、物価の下落によって実質的な債務が増大する。
名目金利の低下で変動型金利の債務(預貯金)の利子収入が減少する。
③ デフレスパイラル
消費支出の減少と企業活動の停滞によって悪循環をもたらす要因となる。
経済全体で供給過多・需要不足⇒物価が低下⇒企業の利益減少⇒従業員の賃金低下⇒名目賃金の下方硬直性と実質賃金の上昇⇒失業者増加⇒家計の収入減少⇒購買力の低下⇒さらなる商品価格の引き下げ⇒名目金利の下方硬直性と実質金利の高止まり⇒実質的な債務負担増⇒借金返済の優先⇒設備投資や住宅投資の縮小
2. デフレ対策
一般に、伝統的・非伝統的といわれるものを含めた金融政策、需給ギャップの解消を円滑とするよう足並みをそろえた積極的な財政政策、潜在成長率を引き上げるような規制緩和政策等、政策の機能的な組み合わせが求められる。