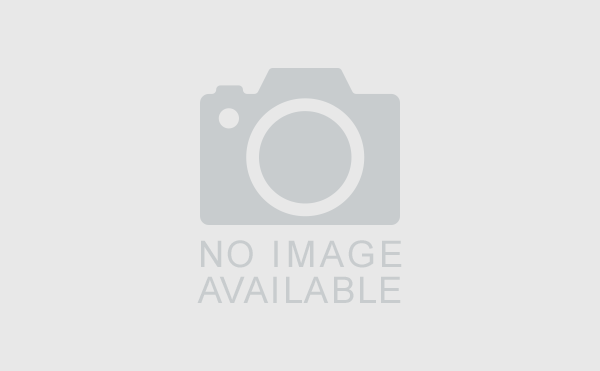Ⅱ-4-3.インフレーション
Ⅱ-4-3.インフレーション
インフレーション: 景気が過熱して物価が継続的に上がっていく現象。貨幣価値の低下。
賃金も物価の上昇に伴って上昇するが、物価に比べると調整に遅れをとるため、短期的には実質賃金が下がり実質所得は低下して家計を圧迫する一方、雇用がしやすくなるので失業率は低下する。
インフレ率が預金金利を上回ると預貯金の価値が実質的に低下する。また、インフレ率が住宅ローンなどの貸し出し金利を上回ると実質的な負債の価値が低下し、その結果実質的な返済負担が減ることになる。
一方、インフレになると期待インフレ率が高まり、実質金利が低下し消費と投資が増大する。
従って、期待インフレ率を上昇させれば実質金利が低下する。
1.インフレの種類
① デマンド・プル・インフレ
需要側に原因があるインフレで、供給を大幅に超える需要があることにより物価が上昇する。
② コスト・プッシュ・インフレ
賃金や原材料費の高騰が原因となり、生産費(賃金、原材料、燃料費)が上昇することで供給側に原因がある。物価水準の上昇と景気後退が同時に発生するスタグフレーションやそれに近い状態になる。
③ 構造インフレ
産業によって成長に格差がある場合、生産性の低い産業の物価が高くなり発生する。
④ 輸出インフレ
輸出の増大により企業が製品を輸出に振り向けたために、国内市場向けの供給量が結果的に減って発生する。
⑤ 輸入インフレ
輸入原材料の高騰など国外のインフレが国内に影響し発生する。
⑥ ボトルネックインフレ
特定の生産要素の不足から、生産(供給)が需要を下回ることによって発生する。
2.その他のインフレ
① 財政インフレ
政府の発行した公債を中央銀行が引き受けることにより、貨幣の供給が増加して発生する。
金融緩和の効果に加えて、財政支出による有効需要創出効果によって需要インフレも発生する。
② 信用インフレ
市内銀行が貸し付けや信用保証を増加させることによって信用貨幣の供給量が増大することから発生するインフレ。
3.インフレの進行度による分類
① クリーピング・インフレ
インフレ率は年間数パーセントで好況期に見られ、穏やかに進む。経済は健全に成長しているとみなされることが多い。マイルド・インフレともいう。
② ギャロッピング・インフレ
早足に進むインフレ。インフレ率は年間数10%。スタグフレーションに伴って生じることがある。
③ ハイパーインフレ
月率50%を超え猛烈な勢いで進行するインフレ。経済の適正水準を超えて政府が通貨を発行益の獲得を図る場合に発生する。
2. 対策とスタグフレーション
インフレの時には超過需要を解消させる必要がある。
① マネーサプライを減らす
② 財政支出を削減する
③ 増税をして消費を抑える
インフレと景気後退が同時に発生することをスタグフレーションという。