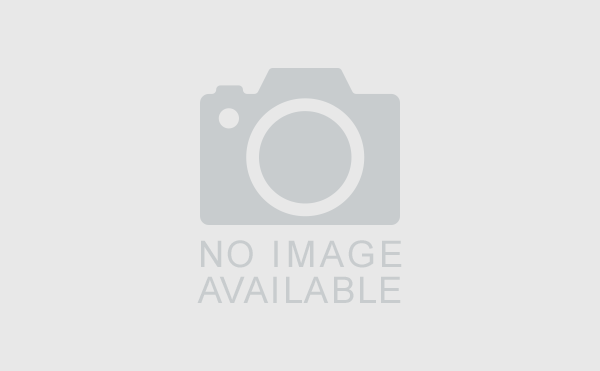Ⅱ-4-1.金融政策
Ⅱ-4.金融政策と株価
Ⅱ-4-1.金融政策
金融政策: 物価の安定を図ることを通じて国民生活の健全な発展に資するため、通貨および金融の調整を行うことを目的に日本銀行が実施する。基本方針は原則年8回開催される日本銀行政策決定会合で決定される。
金融政策の手段は、
① 公開市場操作
② 基準割引率および基準貸付利率(かつての公定歩合)
③ 預金準備率操作
補完手段として、
④ 窓口指導
⑤ 選択的信用規制等
発動まで手続きに時間のかかる日数を要する財政政策に比べ、金融政策は日本銀行政策決定委員会の決定のみで実施されるため機動的といえるが、通貨供給・金利の変動を通じた経済への影響は間接的であるため、有効需要に直接働きかける財政政策に比べ、その波及効果は相対的に遅いと言われる。
株価と金融政策の関係については、単純な図式では語れないが、例えば「金融相場・逆金融相場」、「資産効果・逆資産効果」、「政策促進相場」、「政策失望売り」といった株式相場で馴染みのある用語は両社の密接な関係の一端を表している。
1. 金融政策の目的
① 物価の安定
② 経済成長ないし完全雇用の維持
③ 国際収支の均衡
これらの目標には短期的にトレードオフの関係も見られ、全て同時達成は非常に困難であり、いずれかの目標に重点を置いて政策運営されることが多い。
2. 金融政策の手段
① 公開市場操作(オペレーション)
中央銀行が市中の金融機関との間で国債の売買を行い、金融市場の資金需給が変化し、これを受けた金融機関の企業貸出金利などへの波及を通じて経済活動全体に金融政策の波及が及ぶことを目指す。
② 基準割引率および基準貸付利率(かつての公定歩合)
金融機関への貸し出し利率。
③ 預金準備率操作
準備預金制度は金融機関に対して、預金の額の一定率(預金準備率)に相当する金額を日本銀行に準備預金(当座預金)として預けることを義務付ける制度。1991年以降実施されていない。
3. 金融政策運営の手段~2段階アプローチと誘導型アプローチ
運営方法には、
① 2段階アプローチ
まず中間目標を置き、その達成を媒介として最終目標を実現しようとする運営。
② 誘導型アプローチ
中間目標を置かずに操作変数から直接的に最終目標を実現しようとする運営手段。
4. 説明責任と市場との対話
日本銀行は政策委員会の金融政策についての説明責任の一環として、決定会合直後の総裁記者会見、金融政策決定会合の議事要旨を公表する。
「物価の安定」についての基本的な考え方を改めて整理するとともに、中長期的に見て物価が安定していると理解する物価上昇率(中長期的な物価安定の理解)を示し、これらを念頭に置きながら金融政策運営を行っていくことを明確化した。
5. 金融政策の波及効果(緩和と引き締め)
短期金融市場で金利が下がると、金融機関は低い金利で資金調達ができるので、企業への貸し出しにおいても金利を下げることができる。企業は運転資金や設備資金を借りやすくなり、景気が刺激され、物価の下落圧力が弱まる。
金融市場は互いに連動しているから、銀行貸し出しの金利だけでなく、企業が社債発行などの形で市場から直接資金調達をする際の金利も低下する。
逆に、短期金利市場で金利が上昇すると金融機関は高い金利で資金調達をしなければならず、企業への貸し出しにおいても金利を引き上げる。景気が抑制され、物価の上昇圧力が弱まる。
企業が社債発行などの形で市場から直接資金調達をする際の金利も上昇する。
6. 非伝統的な金融政策
資産デフレ対策として非伝統的政策が実施された。
① ゼロ金利政策
オーバーナイト物無担保コールレートをデフレ懸念の払拭が展望できる情勢になるまで、実質的のゼロに誘導する。
② 量的緩和政策
「当面、日本銀行当座預金残高を5兆円程度に増額し、その政策を消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロパーセントになるまで継続する」というマネタリーベース(現金通貨+日銀当座預金)を目標とした政策。
③ インフレターゲット
より直接的に物価上昇率自体を目標にする政策。
2013年に物価安定の目標について消費者物価の前年比上昇率2%と定めた。