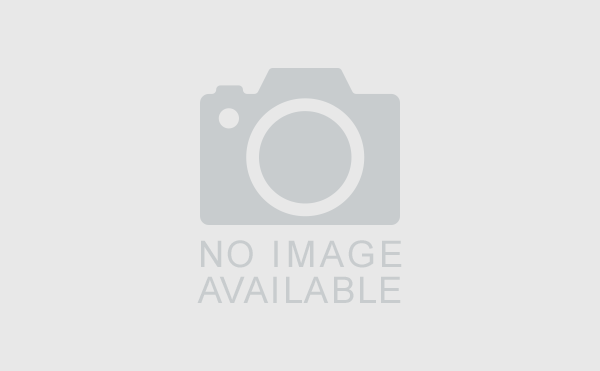Ⅰ-2.テクノ・ファンダメンタル分析について
Ⅰ-2-1.テクノ・ファンダメンタル分析 その1
テクノ・ファンダメンタル: テクニカル分析とファンダメンタル分析の統合。「株価のマクロ分析」
1.ファンダメンタルズの変化に応じて株式市場がどう動くかは、同じようなファンダメンタルズの変化でどう動いたかという過去の動きに聞くしかない。
株価変動をファンダメンタルズ変動と関連付けて整理しているので、将来のファンダメンタルズを予測することによって将来の株価を予測できる。
2.過去の株価変動には繰り返すものと繰り返さないものとがあり、株式相場の各局面をその時々のファンダメンタルズによって分類しているので、過去の変動パターンに必要以上にとらわれず柔軟性に富む。
3.株価とファンダメンタルズを相互チェックしているので、単なるテクニカル分析・ファンダメンタル分析よりもバランス感覚が優れていて、自分の株価見通しやファンダメンタルズの見通しに間違いがあれば、早期に誤りを修正できる。
テクノ・ファンダメンタル分析のツール
1.株価波動と景気循環(トレンドとサイクル)
株価に波動(上昇相場と下降相場)があるのは、景気に循環(好景気と不景気)があるからである。景気循環には「建設循環、設備循環、在庫循環」などがあり、これらの組み合わせで景気の姿と株式市場が決まる。
2.イールド・スプレッド、PER、標準偏差などの理論水準を推定するのにイード・スプレッドとPERを使い株価が属する集合の母集団(上昇相場、下降相場)の推定に標準偏差を使う。
Ⅰ-2-2.テクノ・ファンダメンタル分析 その2
1.株価と景気の原理原則
景気と株価の間には極めて密接な相関関係、先行・遅行関係がある。
株価の原理的に株価の分子は予想キャッシュフロー、分母は資本コスト。
株価はファンダメンタルズの変化を予測し、先取りして動く。
その経済の変化をトータルとしてダイナミックに捉えるには、どうしても景気循環の立場に立つことが重要である。
景気循環論
拡張期(回復期、拡張期)と収縮期(後退期、収縮期)の4つの局面がある。
株価はこれを先取りする形で、しかも株価の分母に含まれる資金コストを構成する無リスク利子率は、分子の利益より先行的な動きを見せる。
・不景気の株高「金融相場」 (一段上げ)
・景気が回復、拡張に向かう「業績相場」 (二段上げ)
・景気が過熱しインフレ懸念される前後に金融引き締めで株価は頂点に達し「逆金融相場」 (一段下げ)
・金融引き締め政策が浸透し景気が後退し企業収益が減益「逆業績相場」 (二段下げ)
株価変動の1サイクルは6局面
金融相場→中間反落→業績相場→逆金融相場→中間反騰→逆業績相場
2.景気の4サイクル
ミクロの企業収益はマクロ景気より先行的に動く。
① 短期、在庫サイクル(40か月)
② 中期、 設備サイクル(10年)
③ 準長期、 建設サイクル(20年)
④ 長期、 技術革新サイクル(50年)