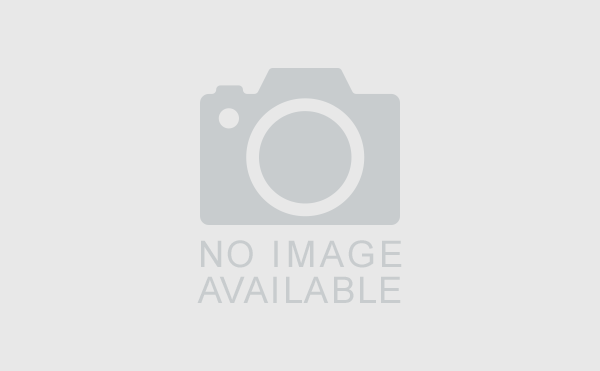安いからという理由で株を買って良いのか?
安いからという理由で株を買ってはいけない
株を買う時には出来るだけ安い価格で買いたいと誰もが考えます。
商売でも仕入れコストが低い方が高く売れた時の利益は大きいです。
逆に安く手放した(損切り)時の損失も小さく済みます。
一般的に株価が下がってきた場合、
・もうここが底だろう
・これ以上は下がらないだろう
・今が仕込み時だ
・お買い得のバーゲンセールだ
このようなかんがえから頃合いの値段で買い注文を出します。
また、含み損を抱えた人は時に難平(ナンピン)に手を出したりします。
値上がりが見込める株は出来るだけ安い値段で買う!
果たしてそうでしょうか?
波動理論的には、逆業績相場の終焉の悲観的な状況から金融相場へ転換したタイミングと期待するわけですが、上がると期待して買った途端に株価が更に下がりたちまち含み損を抱えることになってしまった経験は誰にでもあると思います。
問題は、” それが底だということを誰が決めたのか? ”ということです。
マーケットで株価を動かしているのは需要と供給のバランスです。
その株を欲しい人が多ければ株価は上がります。
逆に持っていたくない人が多ければ株価は下がります。
そのバランスが傾いた時、傾いた方向に株価は動きます。
では、欲しい欲しくないの判断は誰がどのようにするのでしょうか?
ファンダメンタル派は企業業績や経営的数字と株価で判断するでしょう。
テクニカル派は株価チャートで判断します。
どちらが正しくて株価を動かすエネルギーとして強力かとい言うことは一概には言えませんが、ファンダメンタルは判断基準が様々あり買うタイミングも一様ではありません。
上がる瞬間をいかに狙えるかが勝負!
逆にテクニカル分析ではチャート上に「ここ」という判断基準が明確にあります。
もちろん分析に使用する指標や分析者のスキルによって差はありますが、テクニカル分析の原理原則に照らし合わせるとそのポイントが明確になってきます。
テクニカル分析の本質は「需要と供給の拮抗ポイントをいかに見極めるか」これに尽きます。
そして、バランスが崩れる方に仕掛けていきます。
言い換えると、「株を買うのは需要が勝って上がる方にバランスが崩れた瞬間!」と言うことです。
まさに株は上がる瞬間に買う!ということです。
前段の話に戻りますが、テクニカル分析による買い方には「安いから株を買う」というという観点は、一切存在しません。
それがまだまだ下落途中だったら” 落ちていくナイフを素手で握る ”ことになるからです。
・株価がいくら安くても上がらないなら買わない。
・株価がいくら高くてもそこからまだ上がるなら買う。
この観点しか存在しません。
ですから底で買うという判断は存在せず、底を確認した後の上がる瞬間を買う、という買い方になります。
この発想の転換が必要で、ここまで思考を切り換えるのはなかなか難しと思います。
しかし、テクニカル分析の原理原則を学び、参加者(投資家、トレーダー)の心理を読む分析が出来るようになれば誰でも思考を切り換えて行動することが出来るようになります。