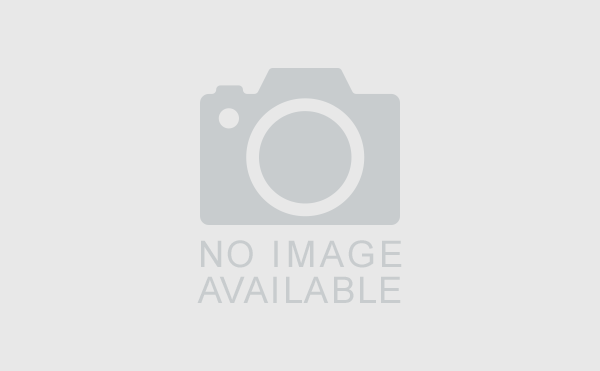株価は企業業績だけでは決まらない
企業業績と株価の関係
上場企業は金融商品取引法により四半期(3か月)ごとに業績内容を開示することが義務づけられています。
日本においては一般的に3月末決算の企業が多く見受けられます。
その場合は4月から新年度がスタートします。
・6月末に四半期決算
・9月末に半期決算
・12月末に四半期決算
・3月末に本決算というスケジュールで年間に4回の決算が行われます。
通常は決算から1か月前後で決算結果が開示され、個人投資家は企業のホームページや、ニュースなどを通してその企業の業績を知ることとなります。
ちなみに、すべての上場企業が3月末決算というわけではなく、例えば日本マクドナルドのような外資系企業は本国の基準に合わせて12月末が決算であったり、社歴が浅い新興企業などは会社設立時の決算時期のままというケースもよくあります。
また、百貨店やスーパーマーケットなどの小売業は2月末が決算というように業界の特殊性も関係しますので投資対象とする企業の決算日は常に確認しておくことが必要です。
さて、決算結果が開示されると業績の良し悪しにより株価が大きく変動することがよくあります。
業績が良ければ急騰したり、悪ければ急落したりする事例はよく目にします。
これをファンダメンタル分析の企業業績という観点から見ると、「業績が良ければ今の株価は企業価値に対して割安だから買い!」、逆に悪ければ「企業価値の低下で割高だから手放す!」という見解になります。
加えて、決算発表時期になると日本経済新聞などに業績が良い企業は発表前と比較して株価が〇%上昇した、あるいは業績の悪い企業は〇%下落したといった内容の記事が載ることで、一般的な個人投資家はあたかも「業績=株価」と考え、自らの投資行動の基準にしがちです。
業績だけを過信しない
ここに興味深い事例を紹介します。
ある企業の決算発表前後の株価の動きに着目しました。
この企業の決算は発表当日の取引が終了した15時半に開示されました。
内容は業績の悪化にともない大幅な赤字を計上したという非常にネガティヴな結果でした。
企業業績という観点からすると、「企業価値の低下により翌日は大きく売り込まれ下落する!」と予想されます。
投資家は決算内容を知り大慌てで売却してくるかもしれません。
もしかしたら寄付きから大きく窓を開けて下げたり、最悪はストップ安になり手放せなくなる懸念もあります。
この企業の株式を保有している投資家は眠れぬ夜を過ごすことになるでしょう。
さて翌朝、株価はどう反応したでしょうか?!
決算発表直前と発表後の株価の動きを株価チャートで解説します。
下図の2つの株価チャートの上図が決算発表直前の株価チャートです。
移動平均線は下向きで株価は底這い状態で低迷しています。
恐らく第3四半期の業績も悪く売られ続けたものと思われます。
そして下図の株価チャートが決算発表日後の株価の動きを表した株価チャートです。


発表翌日の株価は下落するどころか買いが殺到したことによりストップ高で引けました。
大陽線が立ちました。
この企業の株価は業績が最悪であるにも関わらず、なぜ暴騰したのでしょうか?
なぜ下落せず、逆方向である上昇に転じたのでしょうか?
その理由は決算と同時に開示された今期の経営計画にありました。
経営計画には業績を回復させる施策として「今期は黒字化を目指し大幅なリストラを実施します!」という内容が盛り込まれていたのです。
決算は過去の企業活動の成績表、つまり済んでしまった結果報告です。
これに対して経営計画は将来の道筋を投資家に提示したものです。
リストラ策を投資家が好感し、今期の業績回復期待から買われたことにより株価が急騰したというのが理由です。
株価を動かすのは需要と供給の関係
「過去の大赤字 < 将来への道筋」により「供給 < 需要」となったのです。
言い換えれば、「失望 < 期待」。
もし、企業業績という情報だけで判断していたとしたら、間違っても翌日にこの企業の株は買わなかったでしょう。
下手をしたら新規で空売りを仕掛けていたかもしれません。
そうなったら逆に動いたわけですから大損をしていたことになります。
このようにファンダメンタルで投資しようとすると多角的にアンテナを張っておく必要があります。
仮に業績と経営計画の両方の情報を得ることが出来たとしても、今度はどちらを重視すべきなのかを見極める能力が必要になります。
しかし、一般的にはその判断は不可能に近いのではないでしょうか。
ファンダメンタル投資にはこのような難しさが付きまといます。
逆にこれをテクニカル的観点で処理をしようとすると、
業績や経営計画の内容には一切関わらず、ただ単に供給よりも需要が高くなれば買いとなります。
では、どういう状態になれば、「供給 > 需要」と判断すればいいのか?
それを株価チャートから読み解みとき、ピンポイントで仕掛けていくのがテクニカル・アナリストの分析技術を駆使したトレードの醍醐味になります。