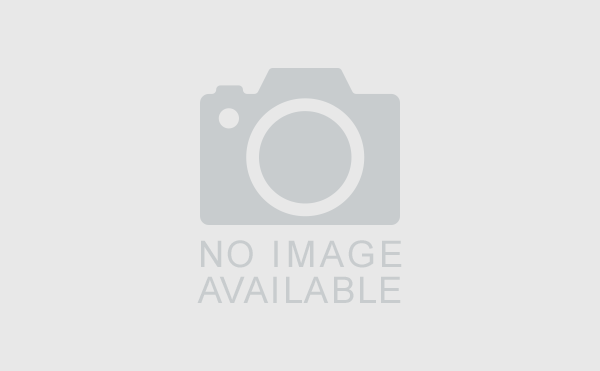今後の日経平均の動き(2018年10月27日)
チャネルラインの信頼性?
2018年10月26日引け後の日経平均株価の日足チャートです。

ろうそく足は、下ヒゲ陰線の出現で底打ち上昇反転しそうに見えますが、金曜日夜間のNYダウは大きく下げ、日経225先物(夜間)も下げています。
日経225先物(夜間)では更に長い下ヒゲをつけたろうそく足が出現し、一旦は下げ止まるような気配が見えています。
しかし、この下落で追証も発生しており、週明けは強制決済によるもう一段の下げと空売りの買い決済とリバウンドを狙った新規の買いが交錯し、株価は素直にリバウンドすることなく乱高下することが予測されます。
テクニカル的にはチャネルラインの下値傾向線までやや余地を残していますので、その下げが下値傾向線で踏み止まるかどうかが注目されます。
さて、このチャネルラインですが、明日以降このレンジは意識されるものの、ここまでの下げの勢いが強かったためにラインの角度が急で、そのレンジ幅も狭いことから、信頼性という意味ではさほど高くないものと思われます。
今後の動きを予測するにあたっては、まずはボラティリティがある程度低下し、値動きが落ち着くまで日柄の経過を待つことになります。
このように株価が急変動している場合は、参加するそれぞれの投資家の思惑、またシステムの判断基準(仕様)が一様ではないためにチャート系システムが機能し難いという特徴があります。
逆に、チャートを意識しないオシレーター系システムによるトレードが幅を利かすことになり、それが相場の変動を更に大きくさせる要因となります。
(しかし、その結果は労は多いものの利は薄い)
ボラティリティが低下するまで日柄経過を待つ
チャート系のテクニカル分析が効果的に機能するためには、まずは相場のボラティリティがある程度低下して、値動きが安定する必要があります。
ボラティリティの安定はボリンジャーバンドで確認していきます。
株価が急落(上昇も同様)している途中のボリンジャーバンド±2σのラインは、共に上下に開いた状態となっています。
下げの勢いが弱まってくると、下向きの-2σに対して先行して上向きであった+2σのラインが下向きの収束方向に転じてきます。
これが急落の勢いが弱まってきた兆候です。
そして、次第に-2σも上向きになり+2σと-2σの乖離が縮小して収束が進んだ状態になるとボラティリティが低下してきたと判断することが出来ます。
そうなると、チャート系テクニカル分析が有効に機能し始めます。
まずは急落の底を確認する
ボラティリティが低下して値動きが安定してくると、この急落における底を確認することが重要になります。
リバーサルフォーメーションの形成を確認しなければ底打ちと判断することは出来ません。
底が確認できるまでにはある程度の日柄を要しますので、今後日々チャートで確認していきます。
(詳細については都度更新していきます)
底打ち後は株価は一時的に上昇し戻り相場となります。
そして戻り高値を付けた後に、次のチャート形成に移っていきます。
大局はふたたびラインに支配される
下図のチャートは2015年8月のチャイナショック、原油値下がり、そして英国のEU離脱までの日経平均株価の日足チャートです。

チャイナショック以降、2か月間の株価は日々ボラティリティをともない不安定に動きました。
その後、11月末までの戻り相場を経て、再度大きく下落する動きとなりました。
この時、戻り高値を付けた時点で、次の下落時の安値、原油安による安値、EU離脱による安値がチャネルラインの下値傾向線によって予測することを出来たことがチャートから読み取ることが出来ます。
また、EU離脱時の安値は原油安で付けた安値をサポートレベルラインとしてしっかり支えられています。
この事実は、NYダウのチャートにおいても全く同じ動きが確認されており、同一のトレードシステムが機能していたことが推察されます。
今回の下落後のチャートにおいても、上記同様に要所要所ではテクニカル的なポイントがサポート、レジスタンスとして意識されチャートを形作ってくることになります。
莫大な資金が同じ意図を持ってそのポイントに集中するからこそ、このようなチャートが作られます。
それをテクニカル分析によって先読みし、仕掛けていくことがテクニカルトレードの目的になります。
概ね3か月~6か月後にはこのような動きを読み取れるようになりますので、近い将来トレンドを狙ったトレードに大きなチャンスが到来します。
急落に際しても目先の動きに右往左往させらずに済む手法も存在するということです。