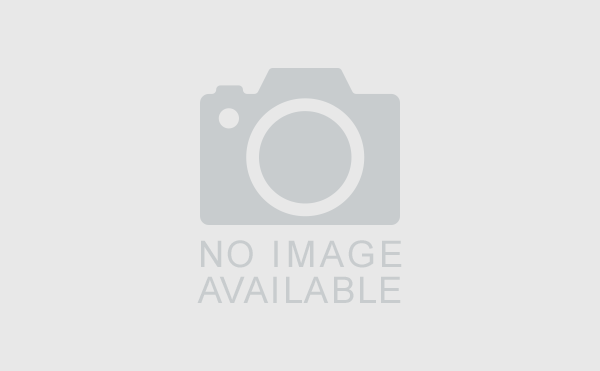グランビルの法則との関係(8628 松井証券、№2)
グランビルの法則との関係
引き続き松井証券(8628)のチャート確認です。
日足チャートに移動平均線を表示させてグランビルの法則から確認してみます。

200日移動平均線に対して75日移動平均線が、75日移動平均線に対して25日移動平均線が収束、発散する動きを繰り返しています。
綺麗なグランビルの法則の複数線の動きです。
株価は2017年9月頃より上昇トレンドに乗って上昇しました。
それに伴い先行して25日移動平均線が、遅れて75日移動平均線が上向きに転じています。
この過程において、25日移動平均線の上昇角度は次第に大きくなり、収束していた25日移動平均線と75日移動平均線が大きく発散する強いトレンドとなりました。
その後株価は、2017年11月に騰落の衰えを示す「上十字」を残し下降に転じています。
これは、エリオット波動的には第3波のインパルス・ウェーブが終わり、第4波のコレクティブ・ウエーブへの流れに転じたことを意味します。
(第1波と第2波は9月中旬に完了しています)
そして第5波の再上昇となったわけですが、ここで重視すべきポイントは25日移動平均線と75日移動平均線の収束にあります。
複数の移動平均線を使い買いポイントを探るには、グランビルの法則に則った視点が必須になります。
複数の移動平均線が極力収束している状態の時に、株価が移動平均線を上回り放れた時のパワーが最も強く望ましい状態です。
そして、更に精度を高めるためのレジスタンスラインを引きますが、このラインは移動平均線の収束がより進んだ局面まで待ってから引きます。
その理由は、移動平均線が発散したままの状態ではボラティリティが大きくダマされる可能性が高いからです。
また、移動平均線が収束していない状態では、下に位置する方の移動平均線に向けて更に下落するリスクを含むからです。
複数の移動平均線が発散したままの状態では、レジスタンスライン自体の信頼性が低くなります。
ベストチャートは、移動平均線が収束している状態にレジスタンスラインが重なっている状態です。
その状態の時に株価が上放れすると強い上昇となります。
(併せて一目均衡表も確認します)
結果、押しの第4波は移動平均線の収束度合いが高まり4本目のファンラインを抜けた時点で終了し、2018年1月から第5波がスタートしました。
チャート上のポイント(A)です。
そこが最適なポイントであったことは、株価が25日移動平均線とレジスタンスラインを抜けた日のろうそく足が窓を空けた大陽線となっていることからも分かります。
同様にポイント(B)も収束した2本の移動平均線とラインの全てが抜けたタイミングとなり、ポイント(C)でも同じ現象となっています。
この様に、複数の移動平均線と株価の関係においても、テクニカル分析の適合性が高いことが確認できます。
今後の展開予測
今後、移動平均線の収束の観点と株価の動きから新たなポイントを探すことになります。

まず8月30日高値を起点とするライン①が存在します。
正規のトレンドラインは9月25日高値を通過するラインですが、乖離した2本のろうそく足を除外して引いた場合、4つの高値が意識され通過することからインターナル・トレンドラインとして採用して良いでしょう。
但し、将来的にこの正規のトレンドラインを延長した位置に株価が到達した場合、強いレジスタンスラインとして意識される可能性が高いことを忘れてはいけません。
そして、その下値傾向線であるライン②が存在します。
先週末の相場全体が急落した日、そしてその翌日もこの下値傾向線がサポートとなり株価は踏み止まる動きとなっています。
今後観測されるチャートの特徴として以下の2つがあげられます。
1.数日後にライン①は25日移動平均線の下に潜り込む
2.数日後に下値傾向線のライン②とサポートレベルラインであるライン③は75日移動平均線の下に潜り込む
3.25日移動平均線は株価がこの付近で推移すると応答基準日の関係から下向きに転じ、ライン①と同じ角度で重なりながら下降する
最も理想的なチャートは、株価がこれら上限、下限の間を推移しながら日柄をこなし、移動平均線が更に収束してインターナル・レジスタンスラインと25日移動平均線が重なるポイントを上抜ける動きです。
高値から2か月の日柄経過後、2本の移動平均線が収束し、25日移動平均線とインターナル・レジスタンスラインの重なりを抜けると非常にポジティブなチャートが出来上がります。
加えて、一目均衡表も三役好転し、株価が横ばいに推移することでボリンジャーバンドの収束が進みます。
そのタイミングでの上放れは、勢いをともなった次の上昇波を迎えるにはベストなチャートです。
ただし、相場全体の流れには大きく影響を受けますのでフラィング放れによる上昇、あるいはサポートが機能せずに下落してしまうことも多々ありますから、全体の流れには注意をしておくことが重要です。