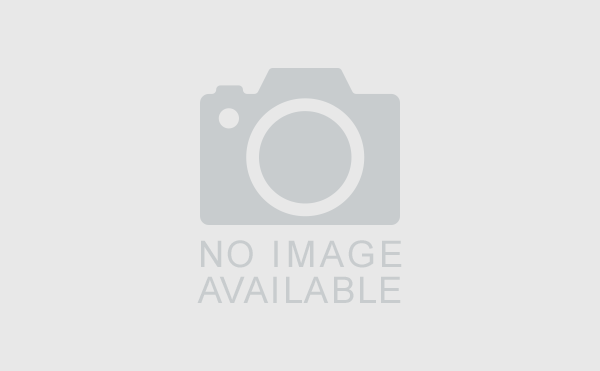Ⅴ-7-1.サイクル分析
Ⅴ-7.サイクル分析
Ⅴ-7-1.サイクル分析
サイクルとは、時間循環(タイムサイクル)を意味する。
株式市場において40か月前後のサイクルが存在するということが否定される可能性は、統計的計算結果ではわずか1万分の2であるとされる。
① コンドラチェフ、 長期、 約50年、 技術革新、戦争
② クズネッツ、 準長期、 約20年、 建設投資
③ ジュグラー、 中期、 約10年、 設備投資
④ チキン、 短期、 約40か月、 在庫投資
1.コンドラチェフサイクル(長期循環)
過去140年間で2.5サイクルという循環的な長期波動が存在する可能性がある。
転換点にはそれぞれ数年の幅があり、サイクルの期間を正確に指摘することはできないが、 期末年で計算すると、第1波は約60年、第2波は45年と平均は50年強となる。
長期サイクルを引き起こす要因として、戦争、技術革新、金産出、農業等を挙げ、資本主義経済における長期波動はこれらの諸要因全部を相互に結び付けることにより説明可能とした。
① 長期サイクルの上昇期は中期サイクルも好況期が長く、同サイクルの下降期は中期サイクルも不況期が続く。
② 長期サイクルの下降期には特に農業が長期にわたり停滞する。
③ 長期サイクルの下降期には多くの生産・交通技術上の発明、発見が行われ、これが次の長期サイクルの上昇期に入って実現される。
④ 長期サイクルの上昇開始期には金の産出が増大し、また植民地の組み入れにより世界市場が拡大する。
⑤ 長期サイクルの上昇期には戦争および国内の社会不安が多発、激化する。
2.クズネッツサイクル(準長期循環)
実質GDPの成長率にはほぼ20年の成長循環があることを発見した。
建設景気循環と同じ周期なので建設循環とも呼ばれる。
3.ジュグラーサイクル(中期循環)
設備投資の変動により生じるので設備投資循環ともいわれる。
設備投資は供給力の増大をもたらすとともに、設備投資自体が需要を喚起するという投資の二重効果を持っているため、設備投資の動向は景気変動、および経済成長のダイナミックな変動要因となる。
設備投資の目的には、
①既存設備の維持更新
②生産能力拡充
③新規事業開発
④合理化・省力化などがある。
4.チキンサイクル(短期循環)
在庫循環とも呼ばれ、われわれの日常生活の中で身近に経験している景気の波である。
企業は通常、販売量に対して一定の比率の在庫量を保有しようとするが、現実の販売市場では需要超過、あるいは供給過剰は発生し、在庫量と販売量の間にギャップが生じる。この在庫量の調整がいわゆる在庫調整となる。
設備調整よりも在庫調整の方が短期間に調整が起こる。